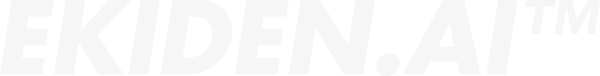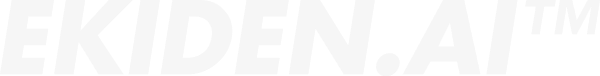コーチの存在意義とは何か — 人間コーチがいない世界を想像してみる
コーチの存在意義とは何か — 人間コーチがいない世界を想像してみる
「コーチングの未来って何だろう?」
「人間のコーチがいないコーチングは成立するのだろうか?」
僕は、重要な試合の時にそばにコーチがいてくれることが、どれだけ心強いかを知っている。
Netflixのドラマ『スプリント』を見ていても、コーチの本質は技術の指導だけではなく、選手の心の支えであることが伝わってきた。
だからこそ、僕は人間のコーチの存在を信じている。
しかし、少しだけ視点を変えて、一回箱の外に出て考えてみた。
もし人間のコーチがいない世界が来たらどうなるのか。
今、AIやデータ解析の技術は飛躍的に進化し、トレーニングメニューの最適化やパフォーマンス予測をAIが担う時代が近づいている。
ストラバのデータや心拍、気温、体調の情報を読み取り、瞬時に適切なアドバイスを出すことも夢ではない。
だが、ここで立ち止まって考えたい。
AIが完璧なトレーニングプランを作れても、選手の「心」を動かし、「ここ一番」で背中を押せる存在になれるのか?
「Coach」という言葉の由来を知ると、その答えが見えてくる。
コーチの語源は、ハンガリーの「コチ(Kocs)」という地名に由来している。
この地で作られた馬車は非常に高性能で、乗る人を安全かつ快適に目的地まで送り届けることで知られていた。
19世紀にはヨーロッパ各地で「馬車=コチ」と呼ばれるようになり、そこから転じて
「人を目的地まで導く存在」として「Coach」という言葉が生まれたのだ。
つまり、コーチとは単なる指導者やアドバイザーではなく、
「大切な人を、その人が望む場所までしっかり送り届ける伴走者」なのだ。
これを考えると、人間のコーチには、テクノロジーやデータには代えられない「心の通い合い」があることがわかる。
選手の悩み、緊張、不安を理解し、それを乗り越えさせる力。
一緒に汗を流し、時に叱咤し、時に励まし、共に勝利を喜び合う存在。
だからこそ、どんなにAIが進化しても、人間のコーチが完全に不要になる世界は想像しにくい。
むしろ、テクノロジーの進化は、コーチの役割をより「人間の心に寄り添う部分」にシフトさせるのかもしれない。
僕たちは今、プロダクトを進化させながらも、
コーチングの根幹である「人と人の信頼関係」を大切にし続けている。
これが、僕が考える「コーチの存在意義」だ。